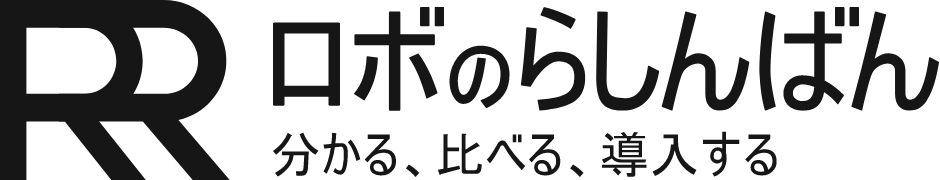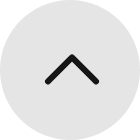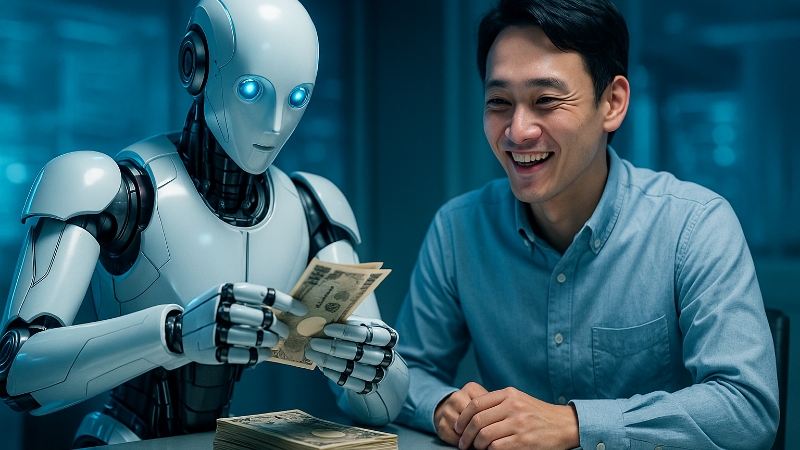
2025.06.20
介護ロボットの補助金ガイド!【2025版】よくわかる申請方法・注意点まとめ
\ ドモ、ミライから来た案内ロボ、アシスタッス /
今日はちょっと先の未来、2035年の介護現場へ、みんなを連れてくッスよ!
実は未来の介護ロボットは進化してて、なんと一家に一台あるのが普通になってるッス!
ロボットがリハビリや自立をサポートして、生活の質がグーンとアップした社会で、みんなが笑顔で毎日を過ごす。こんな未来、はやく体験してみたくないッスか?
今回はそんな未来を実現するための「補助金」についてッス!
「補助金って言葉は聞くけど、書類とかメンドくさそう…」そんな風に思っている介護現場の皆さん!
この記事を読めば、そのモヤモヤ、全部スッキリ解決するッスよ!
介護ロボット補助金のもっと詳しい内容は、↓スクロールして本編記事をチェック!
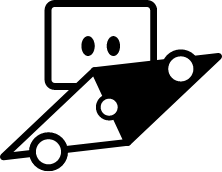
1. なぜ今「介護ロボット導入」と「補助金」が注目されるの?

職員の「腰が痛い」をへらすお助けマシン
「そもそも、なんで国はそんなに熱心に介護ロボット導入を応援しているの?」そう思いますよね。その背景には、日本の介護が直面している大きな課題と、テクノロジーで切り開こうとする未来への強い期待があるのです。
日本の高齢化は、世界でも類を見ない速さで進んでいます。介護を必要とする方は年々増加しており、一方で、介護を支える人材の確保は非常に厳しい状況です。厚生労働省のデータによれば、2040年度には、現在よりもさらに約69万人*¹もの介護職員が必要になると予測されています。
この深刻な「人手不足」は、介護職員一人ひとりの業務負担を増大させ、介護サービスの質の維持・向上にも大きな影響を与えかねません。だからこそ、国や地方自治体は、「介護ロボット」や「ICT(情報通信技術)」といった新しいテクノロジーの力を借りて、この状況を改善しようと本気で取り組んでいます。
■出典 *1 第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について
介護ロボットが現場で活躍すると、こんなことが可能に・・・!
- ・移乗介助などの力仕事が軽減され、職員の身体的負担が大きく減る
- ・記録作業や見守り業務が効率化され、利用者と向き合う時間をより多く確保できる
- ・夜間の巡視負担の軽減や事故防止にもつながり、より安全で質の高いケアの提供が期待できる
つまり、補助金制度は、「介護ロボットという先進技術を活用して、介護する人、される人にとっても心地よい社会にしよう!」という、未来に向けた力強いメッセージが込められた制度なのです。
2.【2025年版】超入門!介護ロボット導入に使える「補助金制度」

じゃあ続いては、「具体的にどんな名前の補助金があるの?」という疑問にお答えします。介護ロボット導入を考える際に、特に知っておくべき国の大きな補助金の柱と、地域ならではの支援について、ポイントを絞って分かりやすく解説します。
介護ロボット補助金の王道!「地域医療介護総合確保基金」
介護ロボット導入を検討する上で、まずチェックしたいのがこの「地域医療介護総合確保基金」です。これは国が各都道府県に対して、「あなたの地域で、医療や介護をもっと良くするために、このお金を使ってね!」と渡している、いわば大きな「目的別の予算」のようなものです。
何に使われるお金?
この基金の使い道の一つに、「介護現場の負担軽減や業務効率化のためのテクノロジー導入支援」が明確に位置づけられています。具体的には介護施設や事業所が、その費用の一部を助けてくれます。
対象の使い道(例)
- ・移乗支援ロボット ・見守りセンサーやAIカメラ ・介護記録ソフトやタブレット端末
- ・インカムなどの情報共有ツール ・Wi-Fi環境の整備費用
補助額の目安は?
国が示す大まかな目安としては、導入にかかる費用のおよそ半分(50%)から、多い場合には75%程度となっています。ただし、実際にいくら補助されるか、どんな種類のロボットが対象になるかといった細かいルールは、皆さんの施設がある都道府県が毎年度決定します。*²
*²[出典2:厚生労働省「令和6年度地域医療介護総合確保基金の概要(介護従事者の確保に関する事業 参考資料)」P.3, P.6 など。2025年度(令和7年度)の最新かつ詳細な情報は、必ず各都道府県の公式発表をご確認ください。]
情報の探し方
「〇〇県 地域医療介護総合確保基金 介護ロボット 補助金」のように、ご自身の施設がある都道府県名+関連キーワードで検索すると、最新の募集情報が見つかるはずです。
プラスαのチャンス!「都道府県・市区町村」独自の支援制度
国の大きな制度の他にも、皆さんの施設がある都道府県や市区町村が、地域の実情に合わせて独自に「介護ロボット導入応援します!」という補助金制度を設けていることがあります。
特徴
国の制度では対象外の、地域特有の課題解決に役立つロボットが対象になることも。
また申請の条件が、地元の中小規模の施設に合わせて、比較的シンプルになっていることも多く国の制度の補助金にプラスして、さらに上乗せで補助が受けられることも!
情報の探し方
まずは、ご自身の施設がある都道府県や市区町村のホームページで、「介護ロボット 補助金」「福祉機器 助成」といったキーワードで検索してみましょう。
また、地域の社会福祉協議会や、介護関連の業界団体などに情報がないか聞いてみるのも良い方法です。
3. 補助金の対象になるのは、どんな介護ロボット?
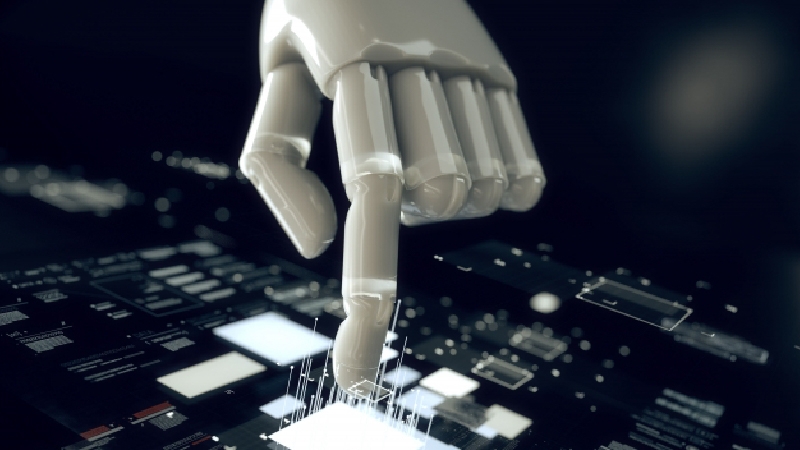
では、具体的に、どんな種類の介護ロボットなら補助金をもらいやすいか?が気になりますよね。
国が特に導入を応援しているのは、介護職員の負担を軽くしたり、利用者さんの安全を守ったり、ケアの質を高めたりする効果が期待できるロボットや技術です。
ここでは、代表的なものを分かりやすくご紹介します。
※実際に補助対象となるかは、必ず申請する自治体の最新の公募要領をご確認ください。
移乗支援ロボット
移乗支援ロボットは、利用者さんをベッドから車椅子へ、車椅子からトイレへなど、抱え上げて移動させる動作をサポートします。
介護で最も腰に負担がかかる作業の一つなので、このロボットの導入効果は絶大です。
例
職員が装着して、持ち上げる力や中腰姿勢を補助するパワーアシストスーツや、利用者を吊り上げて安全に移動させる介護リフトがあります。

起き上がり問題にさようなら!介護シーンを激変する移乗ロボットたち
起き上がり・移乗の負担を軽減!介護現場を変える最新「移乗ロボット」の活用シーンや導入ポイントを徹底解説。
見守り支援ロボット・システム
見守り支援ロボット・システムは 利用者の居室やベッド周りに設置し、離床、転倒、呼吸や心拍などのバイタルサインの異常をセンサーやAI搭載カメラが検知し、職員に知らせます。夜間の巡視負担軽減や事故の早期発見に役立ちます。
例
マットレス下に敷くセンサー、壁や天井に設置する赤外線センサーやレーダーセンサー、AIが映像を解析して異常を通知するカメラシステムなどがあります。

【2025年決定版】介護向け見守りロボット完全ガイド!選び方・種類・補助金までわかりやすく解説 | ロボのらしんばん
介護で注目の“見守りロボット”って?おすすめ機種から選び方、費用、補助金まで、導入前に知りたい情報をまとめて紹介!
排泄支援ロボット・システム
排泄支援ロボット・システは、トイレへの移動を助ける機器から、おむつ内の排泄をセンサーで検知するもの、排泄物の処理を自動で行うロボットトイレまで様々です。利用者さんの尊厳を守りつつ、衛生的なケアと職員の負担軽減を実現します。
例
ポータブルトイレの昇降装置、排泄検知センサー、自動ラップ式トイレなどがあります。
入浴支援ロボット
入浴支援ロボットとは、脱衣所から浴室、浴槽への移動を安全にサポートしたり、洗体の一部を自動で行ったりするロボットです。滑りやすい浴室での転倒リスクを軽減し、利用者も職員も安心して入浴介助を行えるようになります。
例
浴槽に設置するリフト、シャワーチェアのまま浴槽に入れる装置などがあります。
介護業務支援システム(ICTの力で記録・情報共有を効率化)
介護業務支援システムとは、介護記録の入力や管理、ケアプラン作成の支援、職員間の情報共有などを、スマートフォンやタブレット、パソコンを使って効率的に行うためのソフトウェアやシステムです。事務作業の時間を大幅に減らし、利用者と向き合う時間を増やすことを目指します。
例
介護記録ソフト、インカムシステム、バイタル測定機器と連携するシステムなどがあります。
また、これらのICTシステムを施設内でスムーズに活用するためのWi-Fi環境の整備費用も、多くの場合、補助金の対象となりますので、忘れずにチェックしましょう。
4.【これで迷わない!】補助金活用への「最短かんたん5ステップ」

ここでは、具体的な補助金の申請の基本的な流れと、それぞれのステップで押さえるべき大切なポイントを一般的な5つのステップに絞って、お伝えします。
STEP 1:情報収集と計画づくり
まず、施設が抱える課題を明確にし、解決に役立つ介護ロボットやICT機器を検討します。次に、国や自治体の最新の補助金情報を徹底的に調べ、申請に必要な事項を確認。導入機器の選定、具体的な導入計画、期待効果をまとめ、複数業者から見積もりを取りましょう。
重要ポイント
「なぜこの機器が必要か」という目的を具体的に!公募要領を隅々まで読んで、不明点は早めに自治体の担当窓口へ確認すること。それがスムーズな申請の秘訣です。
STEP 2:申請書類の作成と提出
導入計画に基づき、公募要領で指定された申請書、事業計画書、見積書などを作成し、期限までに不備なく提出します。
重要ポイント
申請書類は「審査員へのプレゼン資料」です。具体的なデータ(現状課題の数値化など)を盛り込み、導入後の良い変化を想像させる熱意ある書類を目指しましょう。提出前の複数人チェックも忘れずに。
STEP 3:審査と「交付決定」待ち
提出書類は自治体等により審査され、通過すると「交付決定通知書」が届きます。
重要ポイント
結果を待つ間も準備を進めましょう。そして最重要! この「交付決定通知書」が正式に届くまでは、絶対にロボットの購入契約や支払いを先行しないこと
これが補助金申請の鉄則です。
STEP 4:ロボット導入&活用開始 !
交付決定通知を受け取ったら、計画通りにロボットを購入・設置し、職員研修を行います。契約書、納品書、領収書など、事業実施と経費支出を証明する全書類は、必ず整理・保管してください。
重要ポイント
ロボットは導入してからが本番! 職員全員がスムーズに使えるよう、しっかりとした研修計画と導入後のフォローアップ体制を整えることが成功へのカギです。
STEP 5:実績報告と補助金の受け取り
事業完了後、「実績報告書」を作成し、証拠書類と共に自治体に提出。内容が承認されると、補助金が振り込まれます。
重要ポイント
最後の報告まで丁寧に!
導入ロボットの具体的な活用状況や成果(業務時間削減、負担軽減など)を、写真やデータで分かりやすく報告しましょう。これが次の支援にも繋がるかもしれません。
5. 「採択されやすい申請書」3つの黄金ルール

申請書はただ情報を並べるだけでは、なかなか審査員の心には響きません。「この施設を応援したい!」と思わせる、魅力的な申請書のポイントが3つあります。
「物語」を伝える! ~自分たちの課題とロボットへの期待~
「人手が足りず業務が逼迫している」という事実だけでなく、「職員のAさんは、腰に痛みを抱えながらも、利用者Bさんの笑顔を見るために毎日必死で移乗介助を行っています。
このままではAさんの体も、Bさんの安心も守れません。だからこそ、この移乗支援ロボットが必要なのです」のように、現場の具体的なエピソードや、そこにいる人々の想いを交えて語ることで、審査員も感情移入しやすくなります。
「この課題は深刻だ」「このロボットで本当に助かる人がいる」という共感を生み出すことが重要です。
「見える化」で納得を! ~導入効果を数字と具体例~
「ロボットを導入すれば業務が効率化されます」という表現では、十分とは言えません。
「この見守りシステムを導入することで、夜間巡視の回数を現在の1時間ごとから2時間ごとに変更でき、1勤務あたり約〇時間の新たな業務時間を創出できる見込みです。
これにより、利用者個別のケア記録の充実や、職員の休憩時間の確保が可能になります」というように、導入後の変化を具体的な行動レベルで、かつ可能な限り数値目標を交えて示すことが説得力を高めます。
「なるほど、これだけ効果があるなら投資する価値がある」と審査員に納得してもらうことが大切です。
「本気度」で信頼を! ~導入後の活用計画と熱意~
「ロボットを導入しました、はい終わり」では、補助金が無駄になってしまうかもしれません。
たとえばですが、「導入後は、メーカー担当者による初期研修に加え、各ユニットリーダーを中心とした月1回の活用勉強会を実施し、3ヶ月後には全常勤職員が主要な機能を操作できるようにします。
また、導入効果を定期的に測定・分析し、その結果を地域の介護事業所連絡会で共有。
地域全体のケア向上にも貢献したいと考えています」といった、導入した機器を確実に使いこなし、その効果を最大限に引き出すための具体的な計画、さらにはその成果を広めていこうという熱意を示すことで、「この施設なら、補助金を活かして素晴らしい成果を上げてくれるだろう」という信頼感を醸成することができま
6. 補助金利用の「まさかの失敗」を防ぐチェックポイント

補助金は、介護現場にとって大きな恵みですが、いくつかの注意点を押さえておかないと、思わぬ失敗に繋がってしまうことも。ここでは、よくある「まさか!」を防ぐための3つのポイントまとめました。
チェックポイント①:「補助金ありき」で選ばない!
~本当に必要なロボットを見極める~
ココをチェック!
- 失敗例 「このロボット、補助率が高いからお得だ!」と飛びついたけど、実際に使ってみたら施設の課題解決にはあまり役立たず、結局使われなくなってしまった…。
- 対策 補助金の情報は大切ですが、それ以上に「自分たちの施設が本当に解決したい課題は何か」「そのためにどんな機能を持つロボットが必要なのか」を徹底的に話し合い、明確にすることが最優先です。課題解決に最適なロボットを選んだ上で、その導入に使える補助金を探す、という順番を間違えないようにしましょう。
チェックポイント②:「買った後」の費用も忘れずに!
ココをチェック!
- 失敗例 「補助金で安く買えた!」と喜んでいたら、毎年の保守契約料や消耗品の交換費用、ソフトウェアの更新料などが思った以上にかかり、予算を圧迫…
- 対策 ロボット導入の見積もりを取る際には、本体価格だけでなく、導入後にかかる可能性のある全ての費用(年間保守料、主な消耗品費、電気代、ソフトウェア利用料など)をリストアップしてもらい、長期的な視点での総コストを把握しましょう。費用対効果を考える上で非常に重要です。
チェックポイント③:誰でも使える?~導入後の研修と定着~
ココをチェック!
- 失敗例 「最新ロボットだから、きっと簡単に使えるはず!」と思っていたら、操作が複雑だったり、一部の職員しか使えなかったりして、思うように活用が進まない…。
- 対策 新しい技術を現場に定着させるためには、しっかりとした導入研修と、その後の継続的なフォローアップが不可欠です。メーカーや販売代理店が提供する研修プログラムの内容や、導入後のサポート体制を事前にしっかり確認しましょう。また、施設内で「ロボット推進リーダー」のような担当者を決め、職員からの質問や困りごとに対応できる体制を作るのも効果的です。
7.【Q&A 】よくある疑問ベスト3 介護ロボット補助金編

ここでは、介護ロボットの補助金について、現場の皆さんからよく寄せられる質問とその回答を、Q&A形式で分かりやすくまとめました。
Q1. どんな種類の介護ロボットでも、必ず補助金の対象になりますか?
A1. 残念ながら、全ての介護ロボットが自動的に補助金の対象となるわけではありません。多くの補助金制度では、国や自治体が定める一定の基準(例えば、安全性や介護業務の効率化・負担軽減効果が客観的に認められること、価格の上限設定など)を満たし、場合によっては事前に「補助対象機器リスト」として登録されている製品が対象となります。
最も重要なのは、申請を検討している都道府県や市区町村が発表する最新の「公募要領」や「補助対象機器リスト」を必ず確認することです。 メーカーや販売代理店に、導入検討中の機器が対象となり得るか事前に問い合わせるのも非常に有効な手段です。
Q2. 補助金はいつ頃もらえるのでしょうか?急いでいるので、先にロボットを購入しても大丈夫?
A2. これは非常に多くの方が気になるポイントですが、原則として、補助金の「交付決定通知」という正式な許可を受け取る前に購入契約を結んだり、支払いを行ったりした機器やサービスは、補助金の対象外となってしまいます。
補助金は、申請書類を提出し、審査を経て「交付しますよ」という決定がなされた後、実際にロボットを導入し、その実績を報告した後に支払われる「後払い」が基本です。焦って先に購入してしまうと、補助金が受け取れなくなる可能性が極めて高いので、絶対に注意してください。
Q3. うちの施設は規模が小さいのですが、それでも補助金を利用することは可能ですか?
A3. はい、もちろんです! 国や多くの自治体は、施設の規模の大小にかかわらず、介護現場全体でテクノロジーの導入を支援しています。
むしろ小規模な事業所でも活用しやすいように、補助金の申請枠が別途設けられていたり、申請手続きが一部簡略化されていたり、導入後のサポートが充実していたりする制度も見られます。 「うちは小さいから無理だろう」と諦めずに、まずは情報を集めてみることが大切です。
8. まとめ:介護ロボット補助金は、未来への強力な味方!
さあ、皆さん!ここまで介護ロボット導入のための補助金でしたが、いかがでしたか?
「補助金って、なんだか遠い世界のハナシ…」って思ってた方も、「よし、ちょっと調べてみようかな!」って気持ちになってくれてたらうれしいです。
介護ロボットやICT技術は、決して魔法の杖じゃない。
でも、介護現場で働く皆さんの知恵と経験、そして利用者さんへの温かい気持ちと組み合わせることで、
「仕事の負担を軽くする」「もっと安全なケアを実現する」「利用者さんとの時間を増やす」っていう、素晴らしい時間を作り出します。
そして、その未来への大きな一歩を金銭面から力強くサポートしてくれるのが、
今回ご紹介した「補助金制度」。
ここまでを踏まえたうえで、ぜひ情報をあつめてみてください。
「ロボのらしんばん」は、これからも、介護の未来を明るく照らす情報を発信します。
さあ、補助金という追い風をしっかり受けて、介護する人もされる人も、みんながもっと輝ける、希望にあふれた新しい介護のカタチを、一緒につくっていきましょう!