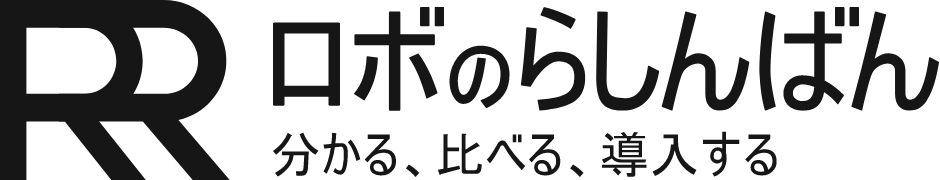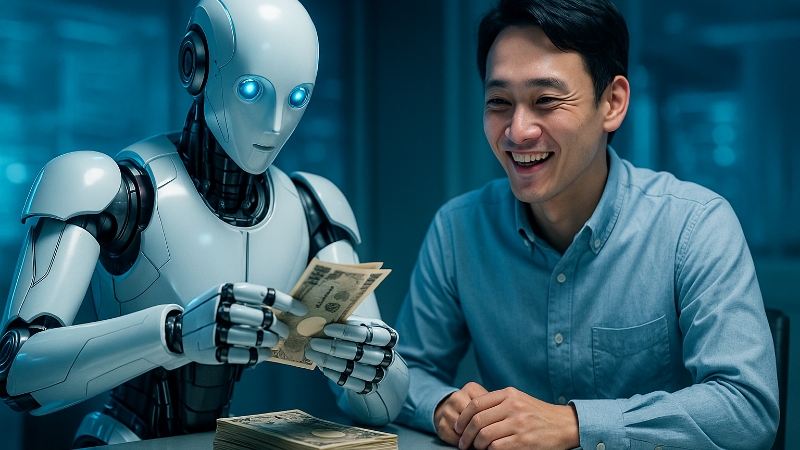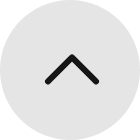2025.06.25
【2025年最新】リハビリロボット紹介!次世代の機能回復とは?効果・種類・選び方まで
\ ドモ、ミライから来た案内ロボ、アシスタッス /
今回は未来の「アシストスーツ」について紹介するッスよ!
「毎日の仕事で、腰や腕がもう限界…」
「もっと楽に、もっと安全に作業を進めたい!」
現場で働く多くの方が、そんな切実な想いを抱えているんじゃないッスか?
でも、 まるでヒーローの装備みたいにあなたの力をアシストし、身体をグーンと軽くしてくれる「アシストスーツ」が今、大きな注目を集めているんス!
「なんか調子いい!」が毎日続いたり、着るだけであなたの体型や作業のクセに合わせて「オーダーメイドフィット」するスーツがでてきたり。
SF映画で見たような空を飛ぶスーツも時間の問題・・・?
未来も気になるッスけど、ひとまず最新のアシストスーツ事情についてまとめたッス!
さあ、未来の働き方を劇的に変える、可能性を探しに行くッス!
見守りロボットのもっと詳しい内容は、↓スクロールして本編記事をチェック!
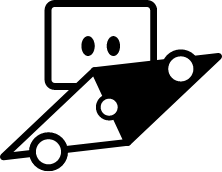
1.リハビリロボットとは?なぜ今、熱い注目を集めているのか
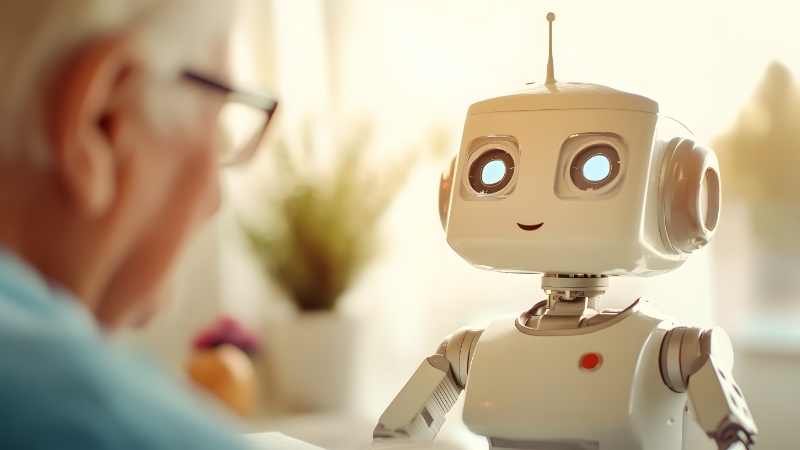
「リハビリロボット」と聞くと、どんなものを想像しますか?もしかしたら、SF映画に出てくるような、少し冷たい機械のイメージを持つ方もいるかもしれません。でも、実際のリハビリロボットは、もっとずっと温かく、そして私たちの「回復したい」という強い想いに寄り添ってくれる頼もしいパートナーなんです。
Keyword
リハビリロボットとは?
病気や怪我、加齢などによって低下してしまった身体機能(例えば、歩く、立つ、手を動かすなど)の回復や維持、向上を助けるロボット。センサー技術、AI(人工知能)などを活用して、より効果的かつ効率的に行うための医療・福祉機器のこと
リハビリロボットは従来の課題を解決し、より科学的根拠に基づいた、個別化された、そして意欲を引き出すリハビリテーションを実現するために、世界中で開発が進められています。
2.注目のリハビリロボット5選
なんだかこれまでの介護ではできないことがたくさんできそうですね。
では、実際にどんなリハビリロボットが活躍しているのかをみてみましょう!
リハビリロボット①
HAL®(ハル)シリーズ(サイバーダイン株式会社)

HAL®は、人が体を動かそうとするときに脳から筋肉へ送られる微弱な「生体電位信号」をセンサーで読み取り、装着者の意思に合わせた動作をアシストする、世界初の装着型サイボーグです。
「HAL®腰タイプ介護支援用」は介護者の腰部負担を軽減し、「HAL®下肢タイプ医療用」は下肢に麻痺がある方などの歩行訓練をサポートします。
- このロボットの特徴 「もう一度、自分の意志で体を動かしたい」そんな切実な願いに、最先端のサイバニクス技術で応えるのがHAL®です。単なる筋力補助ではなく、脳神経系の機能改善を促す可能性を秘めており、リハビリテーションのあり方を大きく変える革新的なロボットと言えます。
- 導入事例・活用シーン 「HAL®腰タイプ介護支援用」:介護施設での移乗介助、入浴介助など、腰に負担のかかる作業の軽減します。また、「HAL®下肢タイプ医療用」:脳卒中や脊髄損傷などによる下肢麻痺患者の歩行機能回復・再学習のためのリハビリテーション。進行性神経筋難病患者の機能維持。
- 導入費用の目安
本体価格:「HAL®下肢タイプ医療用」は高額な医療機器のため個別見積もり。
レンタル:「HAL®腰タイプ介護支援用」は法人向けレンタルプランが中心(月額数万円~)。「HAL®下肢タイプ単関節」など個人向け自費レンタルプログラムも存在(詳細は要問合せ)。
備考:医療用モデルは一部疾患に対し「サイバーダイン治療」として医療保険適用あり。 - 公式情報はこちらでチェック! サイバーダイン株式会社 公式サイト : https://www.cyberdyne.jp/products/HAL/
リハビリロボット②
Welwalk(ウェルウォーク)WW-2000(トヨタ自動車株式会社)

Welwalk WW-2000は、脳卒中などによる下肢麻痺からの機能回復を目指す患者さんのために、トヨタ自動車が開発したリハビリテーション支援ロボットです。
患者さん一人ひとりの状態に合わせて、歩行に必要なサポートを細かく調整でき、より自然で効率的な歩行訓練をサポートします。
- このロボットの特徴 自動車開発で培われた高度なロボット技術と、リハビリテーション現場のニーズを融合させた一台。患者さんの「もっと歩けるようになりたい」という意欲を引き出し、データに基づいた客観的な評価と個別化された訓練メニューで、質の高いリハビリテーションの実現に貢献します。
- 導入事例・活用シーン 病院やリハビリテーション専門施設での、脳卒中や整形外科疾患などによる下肢麻痺患者の歩行訓練。回復期リハビリテーション病棟などで、集中的な歩行訓練を通じて早期の在宅復帰を目指す場合。また患者のモチベーションを高めるための、ゲーム性を取り入れた訓練プログラムの提供などに活用。
- 導入費用の目安
本体価格:主に医療機関・リハビリ施設向けの製品であり、数千万円規模
レンタル:月額レンタル料(例:100万円前後)での提供が中心
月額利用料:レンタル料に保守サポートが含まれる場合が多いですが、詳細は契約によります。 - 公式情報はこちらでチェック! トヨタ自動車株式会社 Welwalk公式サイト: https://welwalk.jp/robotics/welwalk/
リハビリロボット③
Curara(クララ)(AssistMotion株式会社)

Curaraは、加齢や事故、病気などによって歩行が難しくなってしまった人のための、装着型の歩行トレーニングロボットです。
「がんばらないリハビリ」をコンセプトに、利用者の自発的な動きを優しくアシストし、無理なく、そして楽しくトレーニングを継続できるよう設計されています。軽量でコンパクトなデザインも素敵です。
- このロボットの特徴 「リハビリはつらいもの」というイメージを覆し、続けられそうと思わせてくれる、利用者に寄り添った優しい設計が魅力。日常生活の中での「もう一度、自分の力で歩きたい」という願いを、さりげなくそして力強くサポートしてくれるでしょう。
- 導入事例・活用シーン
高齢者施設やデイサービスでの、利用者の歩行能力維持・向上のためのトレーニング。在宅でのリハビリテーションにおいて、療法士の指導のもと、自主トレーニングツールとして活用。
パーキンソン病など、特定の疾患による歩行障害のリハビリ支援などにも向いています。 - 導入費用の目安
本体価格:AssistMotion株式会社または正規販売代理店への問い合わせが必要
月額利用料:クラウド連携などのサービスがある場合、発生する可能性があります。 - 公式情報はこちらでチェック! AssistMotion株式会社 公式サイト: https://assistmotion.jp/
リハビリロボット④
Luna EMG(ルナ イーエムジー)(株式会社松屋R&D)

Luna EMGは、筋電計やトルクセンサーを搭載し、上肢・下肢の運動療法と、その効果測定を同時に行うことができる革新的なリハビリテーションロボットです。
患者さんの微細な筋活動を検知し、それに応じたアシストを提供したり、ゲーム感覚で楽しく取り組める訓練メニューなどを多数搭載しています。
- このロボットの特徴 「治療」と「評価」をシームレスに繋ぎ、データに基づいた質の高いリハビリテーションを実現できる点が最大の強み。多様な訓練モードとゲーム要素で、患者さんのモチベーション維持にも貢献。療法士にとっても、客観的なデータに基づいた効果測定と計画立案が容易になる、頼れるパートナーです。
- 導入事例・活用シーン 病院やリハビリテーション施設での、脳卒中後遺症、整形外科疾患、神経筋疾患など、様々な原因による運動機能障害のリハビリ。上肢(肩、肘、手首)および下肢(股関節、膝、足首)の関節可動域訓練、筋力増強訓練、協調性訓練など。客観的なデータに基づいた、効果的で個別化されたリハビリ計画の設計。
- 導入費用の目安 本体価格:医療機関向けの高機能リハビリテーション機器なので個別見積もり
- 公式情報はこちらでチェック! 株式会社松屋R&D Luna EMG紹介ページ: https://www.matsuyard.co.jp/fields/medical/luna-emg
リハビリロボット⑤
Ouvert(ウーベルト)(株式会社東北医工)

Ouvert(ウーベルト)は、脳卒中などによる片麻痺で動きにくくなった手(手指・手首)の運動機能の再学習を促すために開発された、ロボット型運動訓練装置です。麻痺側の手にロボットを装着し、反対側の健康な手の動きをロボットが鏡のように再現したり、設定された運動プログラムに従って、ロボットが優しく手の動きをアシストします。
- このロボットの特徴 「もう一度、自分の手で物をつかみたい」といった、日常生活に直結する手の機能回復を目指す方にとって希望の光となるロボットです。反復促通療法などのリハビリテーションの考え方に基づいた訓練が可能で、脳の変化する力を引き出し、麻痺した手の再活性化をサポートします。
- 導入事例・活用シーン
病院やリハビリテーション施設における、脳卒中後遺症による上肢(特に手指・手首)麻痺のリハビリテーション。手指の巧緻性(細かい作業を行う能力)の低下に対する機能訓練。
神経疾患や整形外科疾患による手の運動機能障害の改善訓練。 - 導入費用の目安 本体価格:株式会社東北医工または正規販売代理店への問い合わせが必要
- 公式情報はこちらでチェック! 株式会社東北医工 Ouvert製品ページ: https://tohoku-ms.com/ouvert/
3. リハビリロボット導入のメリット

リハビリロボットが仲間入りすると、リハビリの現場や患者さんの毎日に、どんな素晴らしい変化が起こるのでしょうか。そしてその効果を最大限に引き出すためには、どんなことを意識すれば良いのでしょうか。
使って実感!リハビリロボットのメリット
メリット1:「できる!」が増える!機能回復を強力にサポート
ロボットが正確な動きを繰り返しアシストすることで、麻痺した手足の再学習を促したり、弱くなった筋力を効果的に鍛えたりします。これまで諦めかけていた動作が、少しずつできるようになる喜びは計り知れません。
メリット2:「楽しいから続く!」リハビリへの意欲がアップ
ゲーム感覚で取り組める訓練メニューや、目標達成を「見える化」してくれる機能は、単調になりがちなリハビリに楽しさとやりがいをアップ!
「もっと頑張ろう!」という気持ちを自然に引き出してくれます。
メリット3:「客観的データ」で、リハビリ計画がもっと的確に!
ロボットが収集・記録する訓練データ(運動の回数、力の強さ、関節の動く範囲など)は、療法士がリハビリの効果を正確に把握し、一人ひとりに合わせた最適な訓練計画を立てるための、強力な武器になります。
メリット4:療法士の負担を軽減し、専門性をより活かせる!
ロボットが運動のサポートや記録の一部を担うことで、療法士は患者さんとのコミュニケーションや、より専門的な評価・指導により多くの時間を割けるようになります。これはリハビリ全体の質の向上に繋がります。
メリット5:「在宅でも本格リハビリ」が当たり前の未来へ!
小型化や遠隔サポート機能の進化により、病院や施設だけでなく、自宅でも質の高いリハビリを継続できる環境が整いつつあります。これは、患者さんの生活の質向上に大きく貢献します。
4. 【後悔しない!】リハビリロボットの選び方

たくさん種類があるリハビリロボットの中から、「これなら、目標達成を力強くサポートしてくれるはず!」と心から思える、運命の一台(あるいは一つのシステム)を選ぶための、特に重要な「3つの視点」をご紹介します。
視点1:誰の「どんな機能回復」を一番に目指す?
まず一番に考えたいのは、「主に誰が(例:脳卒中後遺症で右半身に麻痺が残るAさん、加齢により歩行が不安定になったBさんなど)」、「身体のどの部分の、どんな機能(例:麻痺した手の指の動き、安定した歩行能力、立ち座りのバランスなど)」を、「どのレベルまで回復させること」を一番の目標とするのか、ということ。「誰の」「どんな状態」に対して、「どんな具体的な目標」を達成したいのかを明確にすることが、最適なリハビリロボット選びの最も大切な出発点です。
視点2:どんな「リハビリ環境」で、誰が主に関わる?
次に大切にしたいのは、そのリハビリロボットを「どこで」「誰が主に操作し、サポートするのか」という、具体的なリハビリ環境をイメージすることです。また、ロボットを操作したり、訓練の準備をしたりする人のITスキルや、新しい機器への習熟度はどれくらいか。設置場所には十分なスペースや電源が確保できるか。
視点3:「続ける楽しさ」と「確かな効果」を両立できるか?
リハビリテーションは、一朝一夕に効果が出るものではなく、ある程度の期間、継続して取り組むことが非常に重要です。だからこそ、「このロボットとなら、楽しく続けられそう!そして、利用者への効果も期待できそう!」と心から思えるかどうかが、大切な基準になります。
訓練は「ゲーム感覚」で楽しめる?効果は「見える化」される?専門家の意見も参考にできる?
これらの視点を持ちながら、情報収集と比較検討を進め、そして可能であれば実際に体験してみることで、きっとあなたや大切な方の「回復への道のり」を力強くサポートしてくれる、最高のパートナーロボットとの出会いが待っているはずです。
5. リハビリロボットの保険適用について

リハビリロボットは高額ですが、保険適用されるケースもあります。ここではどのような保険が適用できるのかご紹介します。
- 医療保険 脳卒中後の歩行障害など、特定の疾患に対するロボット支援リハビリの一部は、医師の指示のもと医療保険の対象となる場合があります。 例えばCYBERDYNE社の「HAL®医療用下肢タイプ」を用いた治療は、いくつかの疾患で保険適用となっています。
- 介護保険
2025年6月時点で、高機能なリハビリロボット自体が「福祉用具貸与(レンタル)」等の対象として広く普及しているケースはまだ多くありません。しかし、歩行補助機能を持つ一部の歩行器などが対象となることはあります。詳しくはケアマネージャーや地域包括支援センターに相談しましょう。
※ただし、対象となるロボットや疾患・条件は細かく定められているため、必ず医師や医療機関にご確認ください。
6. 【Q&A】よくある疑問ベスト3「リハビリロボット編」

ここでは、リハビリロボットについて、現場の皆さんからよく寄せられる質問とその回答を、Q&A形式で分かりやすくまとめました。
Q1. リハビリロボットを使えば、誰でも必ず機能が回復しますか?
A1. リハビリロボットは、機能回復を強力にサポートするツールですが、残念ながら「必ず回復する」と保証するものではありません。回復の度合いは、病気や怪我の種類・重症度、リハビリ開始時期、ご本人の年齢や体力、そして何よりもリハビリへの意欲や努力によって大きく異なります。ロボットは、その努力をより効果的に、そして継続しやすくするためのお手伝いをしてくれます。
Q2. ロボットを使ったリハビリって、なんだか人間味がなくて冷たい感じがしませんか?
A2. そのように感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。しかし、実際には多くのリハビリロボットは、利用者さんが楽しく、そして意欲的に取り組めるように、ゲーム的な要素を取り入れたり、優しい音声で励ましてくれたりする工夫がされています。
そして何より大切なのは、ロボットを使ったリハビリも、必ず理学療法士や作業療法士といった専門家が関わり、利用者さんとコミュニケーションを取りながら進めていくという点です。ロボットは、むしろ療法士が利用者さん一人ひとりとより深く向き合うための時間を生み出してくれる、温かいサポート役とも言えるので
Q3. 最新のリハビリロボットは、操作が難しくて専門家しか使えない?
A3. 医療機関向けの高度なリハビリロボットの中には、専門的な知識や操作スキルが必要なものもあります。しかし、最近では、在宅での利用や、より多くの介護施設で手軽に導入できるように、操作方法をシンプルにし、誰でも直感的に使えるように工夫されたロボットもたくさん登場しています。 また、メーカーや販売代理店による丁寧な導入研修や、分かりやすいマニュアル、充実したサポート体制が提供されている場合がほとんどですので、過度に心配する必要はありません。大切なのは、導入前にしっかりと説明を受け、実際に操作を試してみることです。
7. まとめ:新たなパートナーと未来のリハビリへ
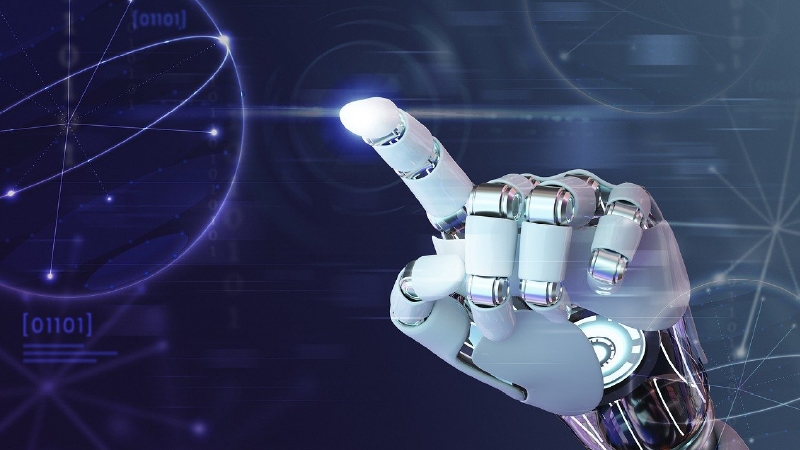
\ さあ、皆さん!「リハビリロボット」が切り拓く、新しい可能性、感じてもらえましたか? /
正確な動きを繰り返しサポートしてくれるかしこさ、
ゲームのように楽しく続けられる工夫、
そして回復の道のりを「見える化」してくれる頼もしさ。
リハビリロボットは、利用者さんと療法士の先生、そしてご家族みんなの「チーム」の一員として、目標達成への道のりを一緒に歩んでくれるかけがえのないパートナーになってくれるはずです。
「ロボのらしんばん」は、これからも、皆さんの「回復したい」という強い想いを全力で応援。リハビリの未来を明るく照らす情報を心を込めて発信していきます。